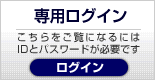新着情報
新着情報

|
2024-04-18 | 4月18日 サヤエンドウ さやむき体験(2年生) |

|
2024-04-17 | 4月18日 委員会活動 |

|
2024-04-16 | 4月16日 給食がスタートしました(1年生) |

|
2024-04-15 | 4月15日 視力検査 |

|
2024-04-12 | 4月12日 ツバメ |

|
2024-04-10 | 4月10日 朝の様子(1年生) |

|
2024-04-08 | 4月8日 着任式・対面式・始業式 |

|
2024-04-05 | 4月5日 入学式 |

|
2024-04-03 | 4月3日 入学式準備 |

|
2024-03-22 | 3月22日 修了式 |

http://sennan-shindachi.jp/
モバイルサイトにアクセス
モバイルサイトにアクセス
106375